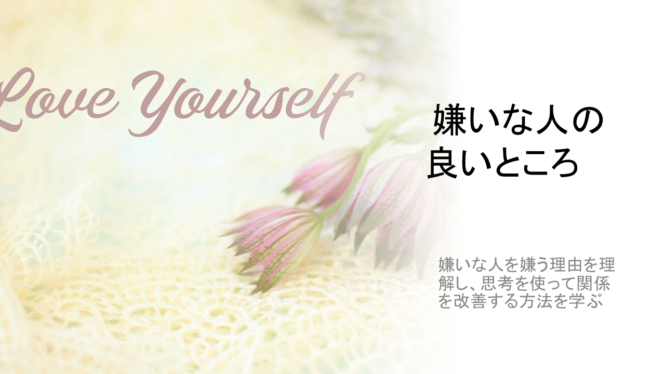
嫌いな人の良いところを見つける
嫌いな人の良いところを考える理由
私たちは日常生活の中で、「なんとなく嫌い」と感じる人がいます。これは本能的な反応として、脳の本能反射領域(脳幹・扁桃体・大脳辺縁系)で作られています。
しかし、この嫌悪感を客観視し、思考(大脳新皮質)を使って「その人の良いところ」を探すことで、人間関係のストレスを軽減し、自分自身の成長にもつなげることができます。
ワーク: 嫌いな人の良いところを見つける
このワークでは、感情や感覚で「嫌い」と感じている理由を客観的に理解し、思考の力を使ってポジティブに変換することを目指します。
ステップ1: 嫌いな人の特徴をリストアップする
- 最近「この人苦手だな」と感じた人を一人選ぶ。
- その人の嫌いな理由をできるだけ具体的に書き出す。
- 例:
- 自慢話ばかりする
- 細かいことを指摘する
- 威圧的な態度を取る
ステップ2: 過去の経験を振り返る
- その人を嫌いだと感じた時、どんな感情が湧いたか?
- 過去に同じような感情を抱いたことはないか?
- 過去の体験が現在の感情に影響を与えていないか?
例: 「自慢話ばかりする人が嫌い」と感じるのは、過去に似たタイプの人に嫌な思いをさせられた経験があるからかもしれない。
ステップ3: その人の強み・良いところを見つける
「嫌い」と感じる部分の裏には、その人の長所が隠れています。そこに注目してみましょう。
- 例:
- 自慢話ばかりする → 実績がある、努力している
- 細かいことを指摘する → 観察力がある、責任感が強い
- 威圧的な態度を取る → リーダーシップがある、決断力がある
まとめ
「嫌い」という感情は、本能的な反応として生まれるものですが、そこに振り回されるのではなく、意識的に「良い面」に目を向けることで人間関係をより良くすることができます。
- 嫌いな人の良い部分をリストアップし、客観的に見つめ直す。
- 「嫌い」の理由が過去の経験に基づいていないかを確認する。
- 大脳新皮質を使い、理性的に考えることでストレスを軽減する。
このワークを日常生活に取り入れることで、よりポジティブな人間関係を築くことができます。
お知らせ
参加者の皆様に、周波数に関する情報をメールでお送りしました。興味のある方はチェックしてみてください。
最後に
今日もご参加ありがとうございました!次回もよろしくお願いします。
学んだことをアウトプットしよう!