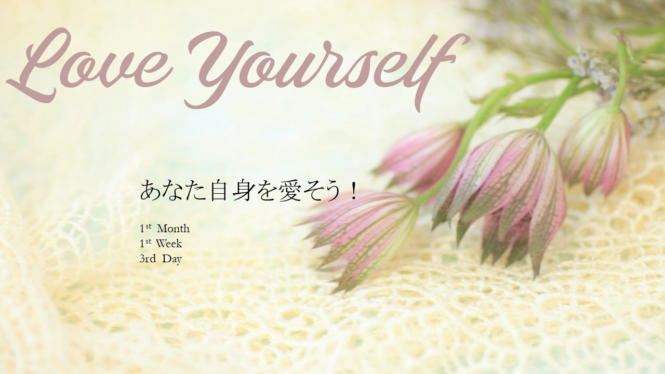
潜在意識をアップデートせよ!
BOOST UP MEETING第九期の3日目として、「脳の構造と四つの意識、自己肯定感を高めるための脳科学的アプローチ」をテーマに進めました。
今日のお話をまとめたのでぜひ最後まで読んで復習してくださいね。
時事ニュースの前半は別記事でご紹介します!
この記事は今朝のBOOST UP MEETINGのまとめです。
- 脳の構造と人間の成長
- 自己肯定感と脳の関係
- 四つの意識と自己肯定感の関係
- 自己肯定感を高める方法
この4つのトピックについてお話しています。
脳の構造と人間の成長
今回は脳の構造と自己肯定感の関係についてお話しました。
脳にはいろいろな部位があるのですが、今回は大きく3つに分けて説明しました。
- 大脳新皮質(外側): 思考を司る部分です。一番外側にあって、私たちの計画や判断を助けます。
- 大脳辺縁系(内側): 感情を司ります。ここに過去の経験が残っていて、自己肯定感に影響を与えます。
- 脳幹・扁桃体(奥): 感覚や生命維持を司る部分で、ストレスや不安が強いと防御モードになります。
人間の脳は、生まれたときは感覚だけでスタートします。
生まれたばかりの頃はお腹がすいたら泣く、おしっこやうんちが出て気持ち悪くなったら泣く。といった感じです。
そして生後1ヶ月くらいで「ニカッ」と笑いはじめます。これが感情の芽生えです。
そして3~4ヶ月になると、何かをつかもうとして手を動かし始めます。
このとき、脳の中で思考が芽生えています。
人間は感覚 → 感情 → 思考の順で育つのですね。
特に感情は10歳以降、思春期に入るとグワーッと大きくなって、感情が爆発したり喧嘩が増えたりします。
一方、思考を司る大脳新皮質は、27~28歳くらいまで成長を続け、30歳前で完成します。
だから、18歳で成人と言われても、脳科学的にはまだまだ成長中です。
28歳で成人でもおかしくないくらいなのです。
自己肯定感と脳の関係
自己肯定感が高い人は、大脳新皮質の前頭前野が発達しています。
ここが発達すると、感情の暴走を抑えられるようになります。
例えば、中学生や高校生の頃は感情が抑えきれなくて大変だったけど、大人になると冷静に考えられるようになるのは、この部分のおかげです。
一方、大脳辺縁系には過去の経験が残っていて、何かあるたびにそれが思い出されて自己肯定感を左右します。
脳幹や扁桃体は、ストレスや不安が強いとコルチゾールというホルモンを出して戦闘モードに入ります。
自己肯定感が低いと、不安や恐れが強くなり、ネガティブ思考が優位になります。
しかし、自己肯定感が高い人は感情をコントロールしやすくて、楽観的になれる。
脳の構造と働きを知ると自己肯定感を高める方法が解ります。
そして脳の使い方を変えると自己肯定感が高まります。
四つの意識と自己肯定感
次に、人間の四つの意識と自己肯定感のつながりについて話しました。
ここからはメンバー限定記事です
こちらの記事はBOOST UP MEETINGに参加されている方用のフォローアップコンテンツです。