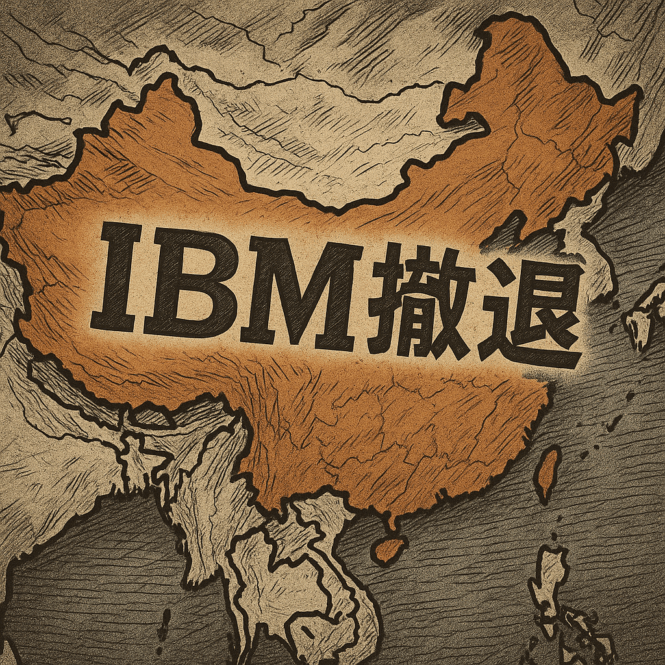
世界的企業の中国撤退と各国の産業戦略
IBMの中国撤退が示す構造転換
IBMが中国からの事業撤退を開始しました。実はこの企業、中国共産党成立以前から中国と深いつながりを持っていたそうです。かつては通信や計算機関連分野で中国の近代化に寄与し、ファーウェイからは「IBMは我々の父」と称されるほどの影響力を持っていました。 しかし、中国とアメリカの対立が激化する中で、中国政府は国内企業の保護と育成に舵を切り、外資の役割は次第に限定的に。IBMも2024年3月頃から撤退を開始し、今では研究開発拠点をインドに移す動きも見せています。
ニトリも静かに縮小:中国ビジネスの限界
日本企業も例外ではありません。例えば、家具チェーンのニトリ。2024年2月には中国で1,000店舗展開を目指すと発表していたにもかかわらず、実際はすでに20店舗以上を閉鎖。中国市場での急速な環境変化が背景にあります。 理由の一つは、中国でのECの発展です。通信販売の利便性が高まり、実店舗を持たない企業に押される形で、ニトリのような従来型のビジネスモデルが通用しにくくなってきているのです。
各国が国内産業の育成にシフト
現在、アメリカ・中国・ロシアはいずれも「自国産業を守り、育てる」という方向に大きく舵を切っています。
- 中国:国産品の利用を推奨し、外国企業への依存度を低下させる政策を推進。
- アメリカ:トランプ大統領以降、「経済安全保障=国防」という考え方が浸透。国内産業の再興に注力しています。
- ロシア:ウクライナ戦争と経済制裁により、外資が撤退。その代替として国内企業が育ち始め、ローカルブランドが台頭しています(例:コカコーラもどきなど)。
こちらの記事はBOOST UP MEETINGに参加されている方用のフォローアップコンテンツです。